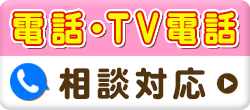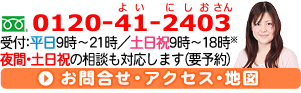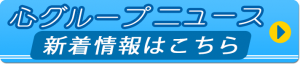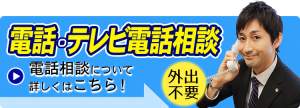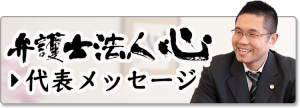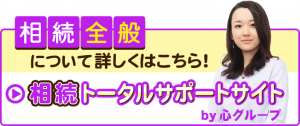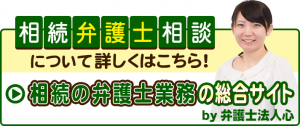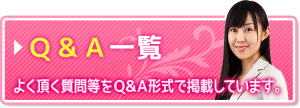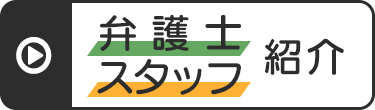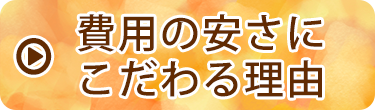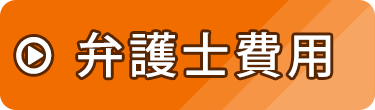相続放棄と限定承認の違い
1 相続人となるか否か
民法922条は、「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。」と規定しています。
つまり、限定承認は相続の承認の一種で、被相続人の相続人になるということになります。
他方、民法939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定していますので、相続放棄を行うと、被相続人の相続人にはならないということになります。
このように、相続放棄と限定承認は、まず、被相続人の相続人となるか否かで違いがあります。
2 相続人全員で行う必要があるか
民法923条は、「相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。」と規定しています。
つまり、相続人が複数存在する場合、限定承認は、共同相続人全員が一緒に行わなければならず、一人でも限定承認に反対する共同相続人が存在する場合は、限定承認はできません。この場合、他の相続人は、単純承認か相続放棄を選択しなければなりません。
他方、相続放棄についてはこのような規定はありませんので、相続人が複数存在していても、他の相続人の意向に関係なく相続放棄の手続きを行うことができます。
3 財産目録の提出を要するか否か
民法924条は、「相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。」と規定しています。
つまり、限定承認の申述を行う際は、被相続人の遺産について財産目録を作成して提出しなければならないということです。
他方、相続放棄にはこのような規定は存在しませんので、相続放棄の申述に当たり被相続人の遺産について財産目録の提出は不要です。
なお、裁判所が用意している相続放棄申述書の書式には被相続人の遺産を記載する箇所がありますが、記載が必須というわけではございません。
遺産が不明であれば、不明と記載すれば問題ございません。
4 遺産の管理について
民法926条1項は、「限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。」と規定しています。
つまり、限定承認を行った相続人は、一定の注意をもって相続財産の管理を継続しなければならないということになります。
他方、相続放棄を行った者の場合、相続放棄を行った時に相続財産に属する財産を現に占有していた場合のみ、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならないとされています(民法940条1項。なお、固有財産におけるのと同一の注意と、自己の財産におけるのと同一の注意というのは同じ注意義務と理解いただいて問題ございません)。
つまり、相続放棄の場合は、一定の条件を満たす場合のみ、管理義務を負うということになります。
以上、相続放棄と限定承認について、主要な4つの違いをご説明しました。これ以外にもいろいろ違いはありますので、ご相談の際に担当弁護士にお尋ねください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒359-1123埼玉県所沢市
日吉町9-23
TRN所沢ビル4F
0120-41-2403